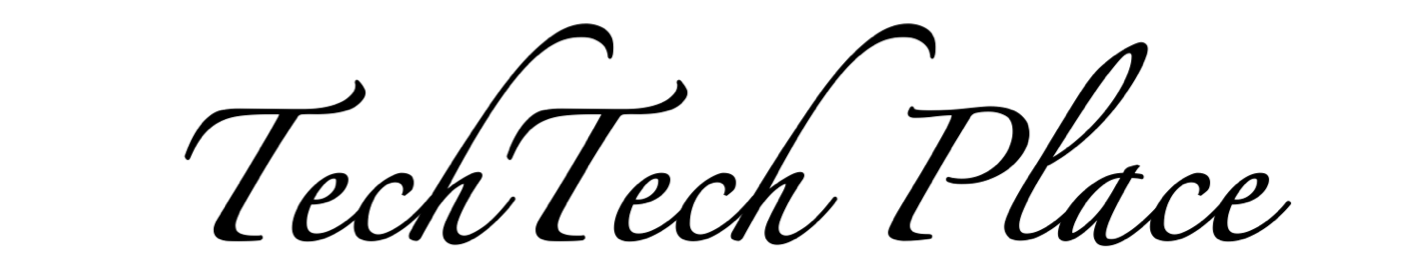こんにちは,しまさん(@shimasan0x00)です.
この記事を執筆しているのは年末です.
編入しての年が終わると考えると感慨深いものがありますね.
公開はいつになるかわかりませんが久々の編入系のお話です.
今回はタイトルにある通り研究室のお話です.
弊学では三年生の後期から研究室に(仮)配属することになります.
ここで(仮)がつくのは4年生になった際に研究着手条件というのがあって,その条件を満たさないと卒業研究できないのです.
簡単にいえば,卒業研究するのに時間確保するため単位とっとけよ!って条件ですね.
つまり単位を与えられていない編入学生にはまぁ辛いものです.
他の大学生よりも多い科目を履修しつつ生きています(笑).
私も研究室に仮配属してからまぁまぁ時間が経ったので私の所属している研究室の話でもしようと思います.
高専から編入した人間がこういうところに行く場合もあるんだなって参考にしていただければと思います.
※ここでは私の研究室を一例に挙げていますが研究室のルールなんてものは先生次第でいくらでも変わりますので気をつけてください.
何の研究をしている研究室なのか
まずは私がどんな研究室にいるかを簡単に紹介します.
タイトルにてすでにネタバレなんですが,
機械学習・データマイニング・自然言語処理がメインの研究室になります.
最近は食情報処理やコミック工学なんかに足を踏み入れていますね.
スポンサーリンク
どうやって研究室を決めたのか
弊学の場合は成績順で好きなところに入れるというわけではなく,平等に機会がある仕組みでした.
研究室の一覧があってその中から第一希望,第二希望を決めます.
各研究室にはもちろん定員がありますので人気のところでは定員オーバーします.
そういう場合はしっかりした面接をして決められます.
定員割れしている研究室なんかは歓談で済んでいたようです笑.
全体としては一応全員面接をしてから研究室に入るという流れです.
私は「高専生が国立大学に編入学するまで」でも書きましたが高専の時代から知っている先生のところに第一志望しました.
それが弊学に来た目的でしたしね.

まぁわかっていましたが定員オーバーでした.
ということで面接して無事希望の研究室に入ることができました.
ちなみに冒頭で成績は関係ないと言いましたが先生によっては成績を考慮するところもあるようです.
私のところはまぁ良ければそりゃいいけど…って感じで重要視はされていませんでした.
スポンサーリンク
研究室に仮配属するとどうなるか
弊学では本格的に卒業研究を行うのは4年生になってからですので3年生はそのための準備期間という立ち位置になります.
私は高専の頃は5年生から研究室の選定,卒業研究に必要なスキルの習得,卒業研究という流れでしたので物理的に時間ができるのはありがたいですね.
では準備期間である私のスケジュールに何が追加されるかというと以下の3つです.
・ゼミ
・輪講
・勉強会
最初の頃はこの3つが別々の日に行われていたので週に3〜4日は大学を出るのが18時〜18時30なんてざらでした.
私はenPiTにも参加しているので1日は仕方ないとして,まぁ帰ったら寝て大学へって感じでした.
普通に単位をとっていた大学生だとこの時期履修科目は1〜3科目ですので全然ライフスタイルが違います.
では3年生である私がそれぞれ何をしているか簡単に説明したいと思います.
ゼミ
これは3年生である私は話を聞くだけの時間になります.
先輩方の進捗報告を聞いたり,先生からの連絡を聞く感じです.
先輩方はLaTeXで作成した資料やPowerPointのスライドなどで説明しています.
知らない技術なんかが出てくるときはすぐに自分で調べたりなんかしていますね.
勝手に自分で作っているプログラムに活かす方法を考えたりしてます.
輪講
大学生,院生含めて一冊の本を輪講しています.
LaTeXで資料にまとめてひたすら話す時間です.
ちなみに今期の本は以下のやつです.
後述しますが初心者向けではないので私は違う本から勉強しています.
輪講で悲しいのはまとめてもあまり読まれないことですね.
プロジェクターでその本を映してるから基本見られないのです…
勉強会
本研究室ではPythonを用いるため,Pythonの文法を本当に簡単に確認したあと以下の本を用いて勉強します.
M1,M2の人と我々3年生で勉強をしていきます.
内容は3年生がそれぞれ分担して簡単に説明しています.
この本は機械学習の基礎を理解するのはいいのですがプログラムに関して(scikit-learn)言えばよくありません.
mglearnというライブラリを使うのですがこの本のために書かれたもので,とりあえずmglearnを使えば解決みたいな書き方で私は「う〜ん」という感じでした.
あと日本語訳がオワっています.
(仮)であるという環境
3年生は研究室に(仮)配属なので研究室の鍵も与えられませんし,与えられているものといえば3年生共用で1台のiMacでしょうか.
高専時代は何故かWin ×1,Linux ×2,サーバー ×1を使っていたのでやっぱこういうもんだよなと思いました.
スポンサーリンク
研究室に入ってから勝手にやってること
ということで使用している本がことごとく私のような初心者殺しでしたので他の本を買って勉強している最中です.
それが「ゼロから作る」シリーズです.
Pythonの使うライブラリはmatplotlibとnumpyだけでニューラルネットワークを作っていきます.
TensorflowやKeras,scikit-learnなどのライブラリ使ってわかったフリする人間にはなりたくなかったので私にうってつけでした.
イチからではなく,「ゼロ」からというだけあってかなり説明が丁寧で私のような初心者向けです.
これで中身がある程度理解できるようになれば自分で好きなようにモデル作れるなと喜んで勉強しています.
あとは,スクレイピングやクローリングなんかもやってます.
最近で言えば60万データくらいを8日くらいかけて取ってくるプログラムを作成してゆるゆるクロールさせてます.
得たデータをゆるゆる分析している最中です.
さいごに
今回は編入してからの研究室のお話でした.
編入生は単位を取らなきゃだし研究室での一定のタスクもこなさなきゃいけないので普通の大学生よりは大変なのは間違いないでしょう.
私の場合はありがたいことに研究室の先生と一緒に大阪の方へ大学の発表を聞きに連れて行ってもらったりしていますし研究も好きなことしていいようです.
まぁ,とりあえず今期頑張って生き残れば研究に取り組めるなって感じです.
また後期履修した科目など諸々は今後書くと思います.
質問等あったら気軽に聞いてください.
こうやって記事を書くことで今後編入する人の参考になればと思います.