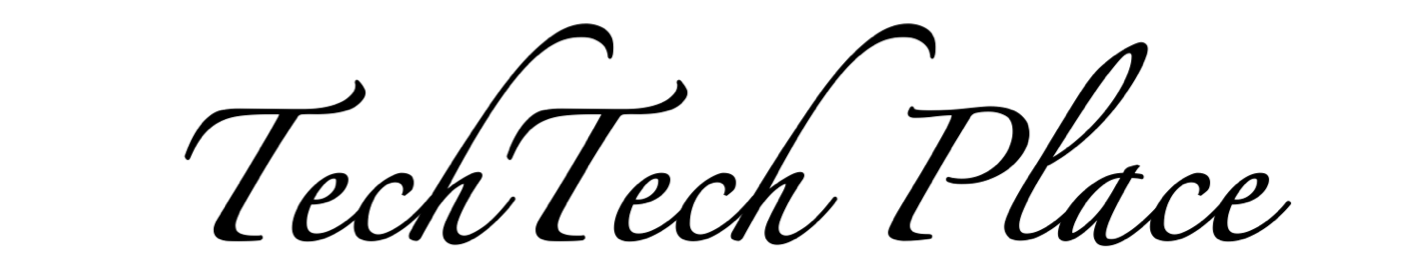こんにちは,しまさん(@shimasan0x00)です.
編入して一息ついたからといって始めたこの「てくてくぷれいす」が出来てもうすぐ2年経ちます.
編入関係の情報が少ないのではないか??という思いから始め,現在はApplePencilを冷蔵庫に貼ったりVTuber関係のデータ分析をしたり,なろうタイトルを自動生成したりとよくわからないメディアとなりました.
アクセスしてくれるユーザさんも多様化し,go.jpドメイン系,大学や企業をはじめとして様々なサイトやSNSでアクセス,紹介していただくようになっています(Instagramまでも.何故??).
そうこうよくわからない記事を生産している間に私が高専から大学に編入して2年経ち,大学を卒業することになりました.
以前,編入エントリを書いたり,編入してからも少し書いていましたが,今回は編入してからを大まかに説明していき,2年間の編入生活を大雑把に振り返ろうと思います.
今後,もっと編入”してから”の情報が増えることを願います.
(思ったまま書いてるので随時更新)
編入1年目(環境への適応と単位履修の巻)
編入してまず最初の登竜門は「環境への適用」でした.
住み慣れていない地方への一人暮らし,そしてメインの専攻の変更です.
今となっては惰性で生活できていますが,慣れるまでは生活に必要な物資,娯楽,病院など知らないことだらけでした.
食事,掃除,洗濯のルーティンや手段を早く確立していると脳死生活できるのでオススメです.
自炊も最初の頃は夢見て色々したものですが,キッチンが狭くて徐々にやる気が削がれましたね.
以下の記事は極端ではあるんですけど,なかなか本質をついている気がします.
レンチンだけの一人用鍋とかもいいですよ.楽で必要なものが摂れますし.
次はメインの専攻の変更です.

上記の記事で書いているのですが,もともとは高専で電気電子工学科というところに所属していました.
主に強電・弱電関連の勉強をし,その他機械系,情報系(制御含む)など色々していましたね.
編入してからは情報系メインの学科のようなものに所属することになり,まずmoodleに驚きました.
高専ではmoodleすら採用されていない学科だったので,課題や講義資料などをmoodle経由で行う先生が多くて,最初はほんとうに課題が提出できているのかビクビクしていたものです笑.
また,編入の際に単位認定があるのですが,もちろん私の多くは電気系の単位が認められ,情報系の単位は2年生向けの講義から履修する必要がありました.
やったことあるけどなぁと思う講義はいくつか散見されましたが,いい復習だと考えて受けてました.
全体的に優しめの講義が多い中,21世紀サイエンス論やデータマイニング,データ構造とアルゴリズム,パターン認識演習,enPiTのNTT基礎研究所での実習など学びの多い講義に出会えたのは幸せでした.
B3では上記のように一般の学生よりは多くの講義を履修し,後期には研究室への仮配属もありました.
もともと編入する前から考えた研究室へ無事,仮配属の面接も終えて入ることに決まったのは僥倖です.
自分がダメダメなのは自分がよく知っていましたから,自身に足りない知識をアップデートしつつ,研究室の空気に慣れる日々を過ごすことでB3は駆け足で終了していきました.
一応講義の成績がそこそこあって表彰もありました.
B3では環境の変化によって,LT始めたりこのblog始めたりエンジニア系のイベントに参加するようになったりと色々動くようになりました.
高専の頃はそんな行動しようとすら思い立たなかったことを考えると大きな変化です.
スポンサーリンク
編入2年目(卒研という名の台風)
編入してから2年目,いわゆるB4は卒研をしていたら嵐のように過ぎ去っていった印象です.
B3で単位の虫となった私は何とか卒研着手条件を満たし,正式に研究室へ配属となりました.
まず,3-4月は何の分野の研究をしたいのかを考え,「ソーシャルメディア上のユーザの動き」を観測することでわかる分析・研究がしたいなとふわっと決めました.
5月には関連のデータを収集,用意ができたので夏前まででかんたんな分析を終わらせ,一区切りできるところまでいきました.
この速度で研究が進んでいったのはデータドリブンの研究をしていたからでしょう(私はData-Driven Research,通称DDRと勝手に呼んでました).
データありきの分析なので,手元にデータはありますからすぐに分析をすることができ,(短期的な視点での)成果はすぐにでます.
また,成果が出るのでモチベーションの維持はしやすいのも特徴でしょう.
しかし,この手法では結果に対する仮説,理由が後付けになることが多く,十分な検証・考察を経ずに進む場合が存在するので迂回して結果に辿り着くなんてことも考えられます.
とまぁDDRによって早めに一区切りついたので,夏休み404することで前期に一度外部発表をし,運良く企業賞を頂くことになりました.
その後は年末までに1,2度ほど外部に出向き,研究しつつ卒論を書いてましたね.
従来の卒論タイムスケジュールであれば12月〜ゆるく書けばいいのかなってイメージだったのですが,B4の年度末に学会に投稿することになっていたので早めに書かなくてはいけなかったのは少しきつかったのかもしれません.
研究室の先生が多忙なこともあって,かなり余裕を持って提出してもチェックして返されるまで時間がかかり,思った以上に試行してクオリティを上げることができなかったのが残念でした.
結局卒論と学会用の論文でデスマに巻き込まれ,あれよあれよと言う間に卒論発表会がすぎ,3月に学会が終わり,ようやく一息????つきました.
大学では学びのフェーズで大学院では研究のフェーズみたいな印象だったのですが,DDRにより思った以上にインプットのない状態でアウトプットをし続け,ドメイン知識が十分に得られていないので,大学院で挽回したいところです.
卒研してたら秒でB4は終わったのですが,学部(学科)のようなもので1位だったらしく,その表彰を受け大学生活は終了です.
(表彰では楯を頂いたのですが,編入なので2年間の在籍なのに4年間の在籍による学修を表彰されるバグが発生しました笑)
スポンサーリンク
雑な総評
- 高専を脳死で生きてるなら編入すると環境が変わり,必ず変化が起きるので自分的には良かった
- もっとインプット時間大事にしよう
- 研究以外のアウトプット大事
- blogでセルフ解決する体験とか面白かった
- 編入でもB4で2〜3回程度は外部発表くらいなら可能(可能なだけ)
- 自分の裁量を把握するべし(マジで)
- まぁデスマ以外は楽しかった
- Apexうまくなりたい