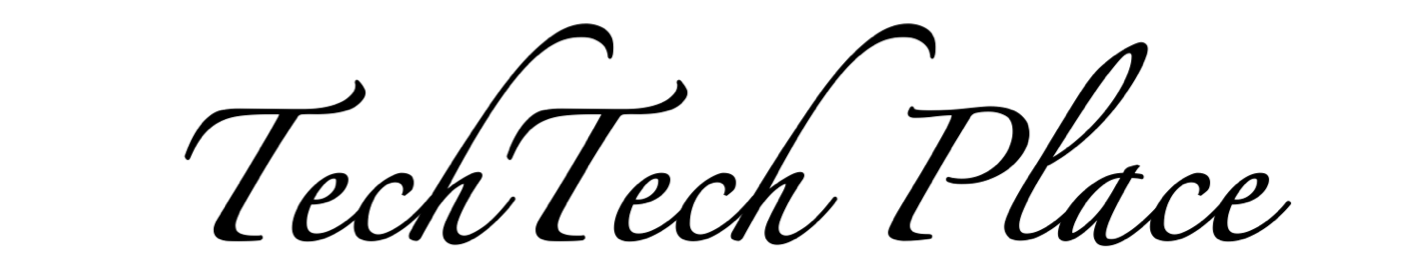こんにちは,しまさん(@shimasan0x00)です.
ここ最近はVTuberに関するデータ分析をしてみたり,V界隈の統計情報を収集するサイト(ShimaStats)を運営してみたりしています.

そんなこんなでゆるく生きていたら,TwitterでVTuberに関する以下の記事がバスっていました.
この記事に対するプラスの意見もマイナスの意見も立場が違えば捉えかたも違うのでその視点での意見は控えますが,「VTuber」というものを自分の中で形作っていこうとしている1ユーザの意見とそのまとめられた歴史については一読すべき内容であったと私は思います.
この記事を読んで私もほんとうにふわっとではあるがVTuber界隈に足を突っ込んでいるしデータ分析もしているので,分析するなかで思ったことや今の「VTuber」というラベルが大きいと感じていることなんかを書いていきたいと思います.
結論を書いちゃうと,にじさんじやホロライブみたいなLIVE主体の活動をするVTuberはVTuberでなく,「Virtual ライバー(or Streamer)」のラベルで区別してほしいと考えています(にじさんじは既に自称していると思うが).
VTuberって何
VTuberについて語っていこうとしているのにその「VTuber」というものが多くの人にはどのような言葉で説明される対象なのかを知っておく必要があります.
Wikipediaによると,
バーチャルYouTuber ( バーチャルユーチューバー、英: virtual YouTuber ) は日本発祥の、コンピュータグラフィックスのキャラクター(アバター)、またキャラクター(アバター)を用いてYouTuberとして動画投稿・配信を行う人。また、その文化。別名:VTuber、Vチューバー(ブイチューバー)
とあります.ただ,VTuberと称している人(以降は人外を称しているもの,人の形を成していないものも便宜上「人」として扱う)でもTwitchなどの他のプラットフォームで活躍している場合があります.「また,その文化」に含有される事象なのでしょう.
また,VTuberは大きく「個人勢」と「企業勢」に分かれます.
個人勢はその名の通り,企画,撮影,編集,PRなどなどの仕事を(多くの場合)一人で行っているVTuberです.
企業勢は私も分析対象としているホロライブやにじさんじといった企業が有名で,演者はLive2Dのモデルや配信機材,PRなどのバックアップを受け取る代わりに広告収入などで得た利益の何割かを企業に納めることで成り立っているVTuberです.
YouTubeにおよそ4割スーパーチャットは持っていかれて企業にn割持っていかれてって考えるとプラットフォームを運営しているAlphabetは日本で起こったVTuberブームは歓迎すべき流れなのだろうと愚考しますね.
スポンサーリンク
分析する前の素朴な疑問
1年前くらいでしょうか.友人から湊あくあを薦められて少し見るようになりました.
それまではキズナアイくらいしか知らないような人間だったのでライブ主体でやっていることにすら当初は驚いていました.
だってそれは配信者なのではないかと思っていたからです.VTuberはYouTubeに動画投稿するユーザであり,ユーザを象徴するものが3Dないし2Dで表現されているだけでよく知っている他のYouTuberと形態が同じだと思っていました(この流れは上記の記事で詳しく説明されてありました).
配信しているけどVTuberであることに時間経過することで慣れていったのですが,その内容について違和感を覚えることがありました.
ゲームの配信,歌の配信,雑談配信,企画配信はわかります.
ただ,誕生日配信,活動XX記念配信だけは???となりました.誕生日配信だけ,活動XX記念配信ならまだわかるのですが,誕生日前日配信や活動XX前記念配信などは正直搾取の構図が目に浮かんでしまって無理でした.
(あと「オフコラボ」という単語を理解するのに少し時間がかかりました.コラボにオンもオフもあるのかって.視聴者はVTuberの”設定”があることを前提としたメタ視点で物事を楽しんでいるんでしょうか.)
最近ではコンスタントな収益源となるメンバーシップのための限定配信として映画の同時視聴が増えているように感じますが,このあたりの反応も視点が違えば意見が変わる部分になるのかもしれません.
最近はTwitchでAmazonPrimeの同時視聴ができるようになるかもといっていましたが,果たして大手は同時視聴だけTwitchでやるように指示するのでしょうか.
私が企業に所属しているVTuberを見ることが多いからかもしれませんが,企業に所属するVTuberって一体何なんだろうと思うようになり,分析してみようと考え実際におこなっていくことになります.
p.s. 個人勢の人だとシャレトンさんが好きです.
スポンサーリンク
分析してみて
イントロ部分でお話していますが,私はここ最近VTuberに関する分析を行っています(後述しますが私が行っているのはVirtual ライバーの分析です).
主に,にじさんじとホロライブに所属するVTuberを対象にして単純な統計量を示すだけでなく,ソーシャルメディアのデータを活用することでネットワーク分析的なアプローチをとったりもしています.



現状は,ソーシャルメディアにおいてユーザ(VTuber)の願望や興味が反映されるのが一方的なフォローから明らかになり,一方的なフォロワー集合はそのユーザを決定させる属性や推すユーザ層が反映されている可能性があることを示唆しています.相互フォローデータからは意味を見出すことができませんでした.通常の社会ネットワークでは重要である相互にエッジが貼られている関係とソーシャルメディアの関係は異なることが改めてわかりました.
にじさんじとホロライブの共通するフォロワーの分布であったり,それら全VTuberをフォローしているユーザが10000名近くいることを明らかにしたりもしました.
TwitterのフォロワーデータからVTuberの類似度ネットワークを作成したこともあります.
企業に所属するがゆえに生じる制約が間接的なデータから明らかになることを望んでいますが,現状新しいアプローチは思いついていません(募集中).
ソーシャルメディアのアカウントは企業と共有しているのは想像できているし,実際にソースを見ると時間指定での投稿(ツイート)があることはわかります.
一応さらなる分析についてはShimaStatsでデータ集めているのでおいおい紹介できたらとは思っています.
ですがこのように私が対象としたのは現状勢いのある企業に所属する配信を主体としているVTuberだけであって,「動画」を投稿するようなVTuberを想定できていないです.
今まで「VTuber」を分析していると言っており,確かに共通認識を得られているからその言葉を持ってしてコミュニケーションできるのはいいのですが個人で思考を垂れ流すときにはVirtual ライバー(or Streamer)と分類したほうがいいのではないかと思い始めています.
Virtual ライバーとするとVTuberは誰なのか
さっき言ったようにVirtual ライバーという名称を使用するとすればにじさんじやホロライブに所属するユーザの殆どは該当するでしょう.
そもそもにじさんじはバーチャルライバーと言っているはずですので問題ないはずです.
しかし,ライブ配信主体のライバーがVTuber界隈で台頭してしまったがゆえに
2D or 3Dのモデルを使用して生配信を主体とする配信者 = VTuber
という式が成り立ってしまったのかなと思います.
スーパーチャットによる商業化の成功や配信であるからこそのインタラクティブ(と思っている)な環境がこの勢いを加速させているのでしょう.
「VTuber」という言葉の意味が変容していっている最中なのかもしれませんね.
ただ,本来のVTuberの定義に基づいたことをVirtual ライバーの人もしているんですよ.
正確にはその人本人がしているわけではありませんが….
「切り抜き動画」ですね.配信は基本的に長時間なので複数みるとN日過ぎてしまいます.
そこで配信の盛り上がりポイントなどを編集して投稿してくれている動画が切り抜き動画です.
主にその配信者のファンの方が作成してくれており,とても出来が良い動画が多いです.
本来YouTuberが撮影している時間が生配信と一致し,編集する行為がファンによって代替されているといえるでしょう(サムネに使用する絵も).
YouTuberがおこなう一連の過程をファンが一部担い,しかもそれが前提でシステムが回っているというのがすごく奇妙であり,かつ新しいなとは思います.
撮影された素材の編集をファンが担っており,それが動画として公開されているのであればそれはファンがVTuberといえるのではないかと私は思ってしまいます.
配信があって実際にコメントを残すのは1%未満のユーザでしょうし,VTuberという存在に対して様々な意味で多大な貢献をしているユーザはこの業界全体でかなり少数でしょうからファンの存在を最後まで尊重できる企業が生存するのかもしれません.燃えたりするとまた別ですが.炎上に関する知見もためていきたいと思います.
スポンサーリンク
結局何
これは私のここ最近思っている思考が垂れ流されているだけです.
重要なのは「VTuber」という言葉の持つ意味が変容しつつあるであろうこと,従来の意味でのVTuberをそのままとするなら今のVTuberはVライバー(or VStreamer)のようなラベルを付けて区別するのがいいのかなと思っているということです.
この記事を後に見たときにまた意味の変容が起きていたり,文化の変容が起きていたりと何かしら変化がおきていることを期待します.