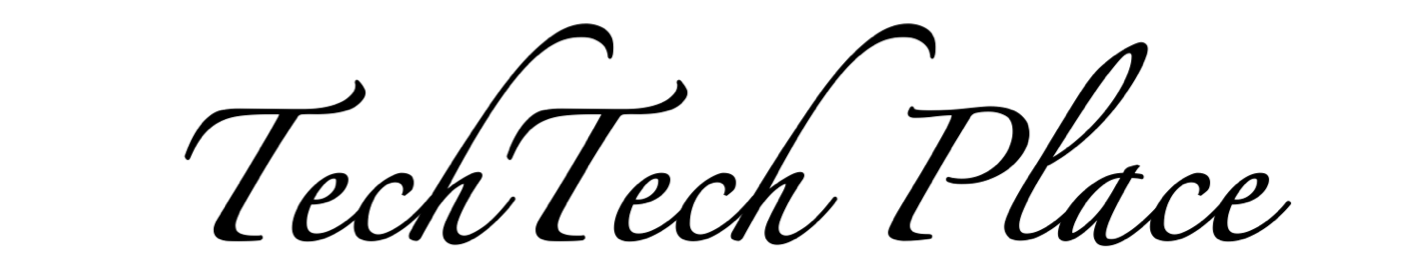こんにちは,しまさん(@shimasan0x00)です.
私は現在研究室に所属して,適度に休みつつ卒業研究に勤しんでいます.
高専の頃を含めれば二度目の卒業研究になりますね(含めていいのかは微妙ですが).
少しずつ少しずつ進めていければなと思いながら生きてます.
そんな卒業研究,研究室ですがこれから研究室に配属されるというかたは「研究室」にどのようなイメージを持たれているでしょうか.
もしくは現在研究室に所属しているかた,所属していたかたはどのようなイメージを持たれていたでしょうか.
私は昔研究室といえば,メンバーが各々の専門領域を修め,研究内容について議論したり頻繁に国際会議の論文の輪講だったりざっくりした紹介があったりとしゅごい所だとイメージしていました.
現在所属している研究室ではメンバーを集めて議論するような場は明確に用意されてはおらず,輪講も論文ではなく書籍です(ゼミのときに論文を紹介する人もいますが).
論文を定期的に読む習慣をつけたり,読んだ論文を発表することによるプレゼンテーション力の向上,議論によるディベート力の向上などがほしい!!!!
でも研究室としてはオフィシャルに行われていない.
では自分達で勝手にやればよくね??
ということで今年度から私主催で始めたKLCについて紹介していきたいなと思います.
※ 始めたばかりでまだまだ未熟なので自分の研究室ではこんなやり方で進めてるよ!なんてご意見いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです.どんどん改良して実りある時間にしたいと思っています.
KLCとは
KLCは「論文を定期的に読む習慣をつけたり,読んだ論文を発表することによるプレゼンテーション力の向上,議論によるディベート力の向上」を主な目的として弊研究室で週に一回開催している会議です.
主に2つのフェーズから成り立っています.
・議論フェーズ(60分)
・論文紹介フェーズ(30分)
それぞれに時間制限が設けられています.限られた時間で結果を出すという経験を積むこと,だらだらしないようにという意味で設けています.
人数は5-6人くらいが望ましいと思っています.多すぎると議論フェーズでまとまりが悪くなったり意見をあまり出さなくなる人が出てくると考えてのことです.
以下では議論フェーズ,論文紹介フェーズの説明をしていきたいと思います.
スポンサーリンク
議論フェーズ
まずは議論フェーズについて紹介します.
議論フェーズでは「あるテーマに沿った議論を定められた時間で行い,何らかの結果を必ず出す」ということを行います.
週一交代で一人が議題を提供する人兼司会を務めます.
議題に制限はありません.既出のものだと以下のようなものがあります.
・人工知能は人間を超えるか
・桃太郎で有能なお供is誰
・トマス・モア「ユートピア」現代版とは
哲学的だろうがフザけた議題だろうが何でもいいと考えています.フザけたものでも突き詰めれば面白い議論ができると思っているからです.
議論フェーズ,論文紹介フェーズともに参加者は共有されたGoogle Documentを使用します.
リアルタイムで意見を書いたりメモを取ったり,ソースを示したりと様々に使用します.

司会の人はプロジェクターで上のdocumentを表示させているので適宜拾いながら話を進めることができます.
- 事前の知識のすり合わせ(単語レベルの認識や事象の関連理解)
- 個々人の意見を集約
- 結論を出す
みたいな流れで進めてたらいいのかなと思って進めてます.
スポンサーリンク
論文紹介フェーズ
次に論文紹介フェーズの紹介をします.
論文紹介フェーズでは自分がしている研究に関連する論文もしくは面白いと思った論文,参加者に有益であると思う論文のいずれかの論文について3分で紹介するフェーズです(できれば国際会議など海外のものが望ましい).
3分なのでスライドは1-3枚程度になります.3分での紹介なので自分の関係ない領域の話でも聞くことができますし,短い時間でその領域の新しい知見を得ることができます.
もしかするとその考えが卒業研究に活かせるかもしれません.
論文を紹介したら共有しているGoogle Documentに自分の紹介した論文の書誌情報を掲載します(Mendeleyなどを使うと楽).こうすることで紹介した論文で興味を持った人はすぐにその論文にアクセスすることができます.
現在はプレゼン資料は集めていないのですが共有フォルダ内に集約できるようにしたいと考えています.
SlideShareやSpeakerDeckなんかに投稿すれば一つの作品になるのかな… .
現状全員が週に一本読んで発表の流れなのですが英語の論文をそんな頻繁に発表できるほど読めるのか難しいので発表する人を分割してしっかり読んだものを紹介してもらう流れがいいのかなって思っています.
さいごに
今回は今年度から勝手に始めた「論文を定期的に読む習慣をつけたり,読んだ論文を発表することによるプレゼンテーション力の向上,議論によるディベート力の向上」を目的とする会議の紹介でした.
はじめにも書きましたが他の研究室ではどのような取り組みをされているか気になるので是非教えてくださいm(_ _)m